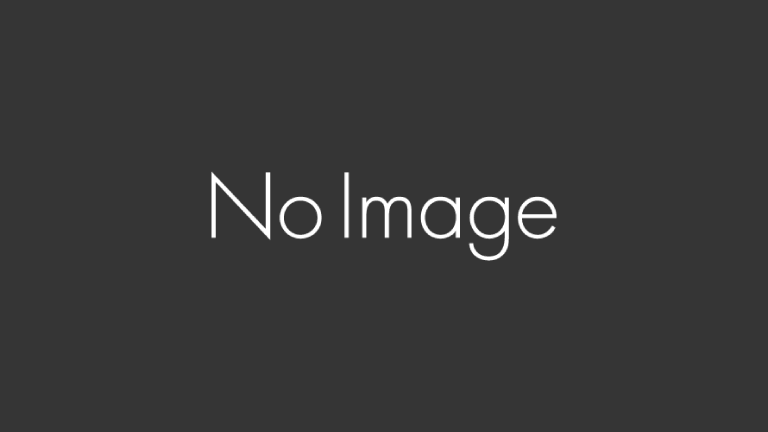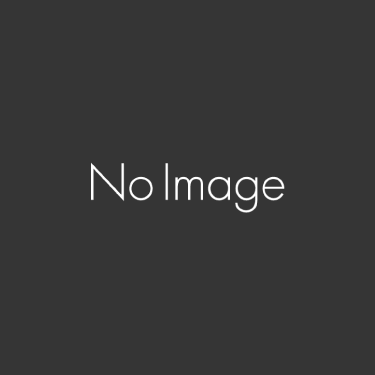触診の目的
・股関節外側面に疼痛を訴える場合
・股関節外側面の圧痛検査として
大腿骨頸部骨折の術後や変形性股関節症で発症することが多く、臨床上頻繁に遭遇する。
特に”歩行のスタンス時”や”片脚立位”といった荷重時に疼痛が誘発されることが多い。
これらは、
「軟部組織に対する伸張ストレス」や「大転子下滑液包に対する摩擦ストレス」が原因で起こることが考えられる。これらに対する整形外科的テストは存在しないため、触知していくと同時に圧痛の確認をとることが重要となる。
また、
深層に位置する「関節包」や「関節唇」にも問題が生じることもあり、これらは体表から触知する事はできない。そのため、整形外科的テストや収縮時痛から鑑別していく必要がある。
大転子の解剖学的特徴
・大転子の前面に小殿筋、外側面に中殿筋(梨状筋)が付着
・大転子の内側面と頸部の境には転子窩があり、内外閉鎖筋や上下双子筋が付着
・大転子を後方から見ると、大転子と小転子を結ぶようにやや隆起した転子間稜があり、大腿方形筋が付着
・大転子前面(AF:Anterior facet):小殿筋が付着
・大転子外側面(LF:Lateral facet):中殿筋前部線維が付着
・大転子上後面(SPF:Superoposterior facet):梨状筋が付着
・大転子後面(PF:Posterior faect):中殿筋後部線維が付着
大転子の臨床との接点
・股関節屈曲45°位では、坐骨結節とASISを結んだ線上に大天使が位置する。これをRoser Nelaton’s Lineと呼ぶ。大天使がこれより上で触れるときは、大転子高位が疑われる。
・中殿筋等の強力な収縮力により、大転子の裂離骨折が生じる場合がある。
・大転子と腸脛靭帯との間の弾発現象を弾発股と呼ぶ
大転子の実際の触診法
1.側臥位にて行う方法
①側臥位。反対側の下肢を屈曲位にて実施。触診する側の股関節を内転位にて大まかな大転子の位置を確認
<大転子の詳細な触診>
・一番突出している部分がSPF
・SPFより少し前方へ進めると骨突起がなだらかになる部分がLF
・さらに前方に進めていくと、骨がなくなる。そこで遠位に進めて骨を追って行くとAFに触れる
・SPFから後方に指を進めると骨がなくなる。そこで遠位に指を進めて骨を追って行くとPFを触れる
2.背臥位にて行う方法
①手掌全体を用い、左右の大腿付近外側を左右同時に挟むように圧迫すると、手掌に大きな骨隆起を感じることができる。これが大転子。
②手掌で大まかな位置を把握したならば、他方の手で他動的に股関節の回旋運動を加える。回旋に伴い、大転子が手掌の下で前後に移動する様子を確認する。
③おおよその大転子の位置が確認できたら、大転子の骨縁を丁寧に触診し、大転子の全形を確認する。指を後方より大転子に当て、小さな回旋を繰り返しながら大転子を近位へと追い、上端部は梨状筋を確認する際のランドマーク。
④上端が確認できたら、同様の操作を繰り返し、下端部を触診。大転子は上下に4〜5cm程度の幅があるため、肢長計測などの際には常に同じポイントを触診できる技術が必要
3.転子間稜(大腿方形筋)の触診
①大転子の後方にあり、大腿骨頭と大腿骨体との移行部にあたる部分。転子間稜の触診は背臥位とし、触診側の股関節を90°屈曲位にする
②股関節中間位の状態で大転子をふれ、指を固定したままゆっくりと股関節を内旋させると、大天使が前方に移動し、大転子の後面を触れる。
③後面を触れたら、指を軽く圧迫しながら遠位へ滑らせていくと、なだらかに窪んでいく転子間稜を触診することができる。中殿筋などの緊張が強く分かりにくいときは、股関節を軽度外転し、筋の緊張を取り除いた肢位で行うと分かりやすい。