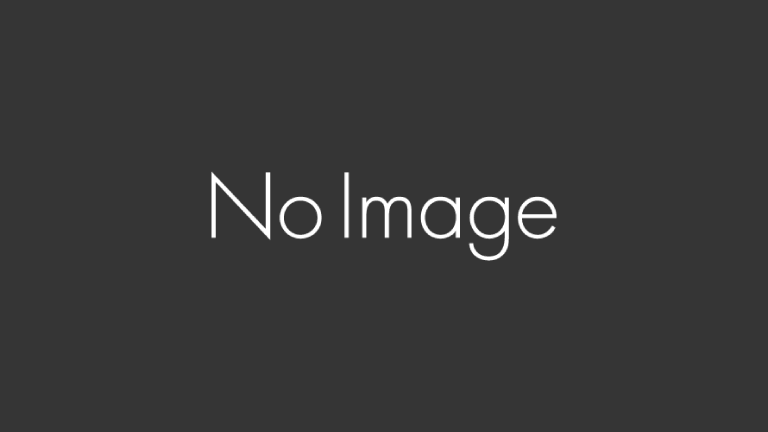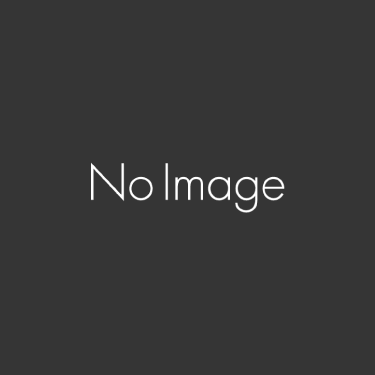触診の目的
・股関節前面痛がある場合
・股関節前面の圧痛検査として
股関節前面の疼痛に関して
その範囲は広く、臨床の現場では膝関節、足関節と違い部位の露出が難しく衣服の上からの触診となる場合が多い。そのためより正確な触診が求められる部位である。
股関節前面痛を主訴とするものに、
①鼠径部痛症候群(GPS:groin pain syndrome)
鼠径ヘルニア、内転筋損傷、恥骨結合炎、腸腰筋損傷
②腸腰筋由来の疼痛
③下前腸骨棘(大腿直筋付着部)由来の疼痛
がある。GPSでは鼠径部内側に疼痛が出現することもある。
◎腸腰筋
大腿骨頭の前方を走行することから、骨頭の安定化作用を有する。このため、腸腰筋の機能低下が生じると、骨頭の前方への動揺性が増加し、股関節屈曲時の前方インピンジメントの原因となる。そのため、腸腰筋の筋緊張を評価する。
◎下前腸骨棘(大腿直筋付着部)
下前腸骨棘は上前腸骨棘の下内側に位置する骨隆起で、大腿直筋の起始となっている。スポーツ動作で股関節の過用が生じると、同部に伸張ストレスが加わり疼痛が誘発される。そのため、”下前腸骨棘の圧痛”、”大腿直筋起始部”の圧痛を検査する。
下前腸骨棘の解剖学的特徴
・上前腸骨棘の下方に下前腸骨棘が位置する
・下前腸骨棘は大腿直筋の起始となる
下前腸骨棘の臨床との接点
・急激な大腿直筋の収縮により、下前腸骨棘に裂離骨折が生じることがある。スポーツ選手では観血的に骨接合術を勧める報告が多い
<関連する疾患>
下前腸骨棘裂離骨折
実際の触診法
1.ASISから1横指下内側にて触診する方法
①背臥位。ASISから1横指下内側に指をずらすと硬い骨に触れる。
2.触診+大腿直筋腱の緊張を確認する方法
①背臥位。示指から環指までの3本の指の上にもう一方の指を乗せASISの付近に当てる。
②乗せた指をやや圧迫しながら、小さな円を描くように2横指ほど内下方へ向かって探ると、小さな骨隆起を感じることができる。これが下前腸骨棘。
③感じた骨隆起に指を置き、下肢伸展挙上運動を行わせると同部にて大腿直筋腱の緊張を触診することが出来る。
大腿直筋の解剖学的特徴
[起始]下前腸骨棘、寛骨臼の上縁および股関節包 [停止]共同腱(大腿四頭筋腱)へ移行後、膝蓋骨を介して脛骨粗面 [支配神経]大腿神経(L2〜L4) [走行]ほぼ大腿骨長軸と一致する [作用]股関節屈曲(外転•外旋)、膝関節伸展・大腿四頭筋の中で唯一の二関節筋
・浅層線維(表面)は羽状構造で速く力強い筋収縮に有利な形態をしている
・深層線維は平行の配列
・幅は中央部で約5cm前後であり、これより近位でも遠位でもその幅は減少する
・大腿四頭筋腱の近位は、大腿直筋と中間広筋との間に滑り込むように侵入し、両筋に挟み込まれる形で結合している
・筋機能の特徴として、下腿の回旋や股関節の内外転にはほとんど作用しない
・共同腱(大腿四頭筋腱)周辺の解剖として、膝蓋骨底部を底辺とした二等辺三角形で頂点は大腿直筋へと続く。大腿直筋の触診は共同腱を基準にすると容易。
大腿直筋の臨床との接点
・大腿四頭筋拘縮症にみられる尻上がり現象は、大腿直筋の短縮を見る検査
・大腿直筋の詳細な短縮の把握には骨盤最大後傾位で膝関節の屈曲角度を計測すると客観性が増す
・Osgood-Schlatter病の発症と大腿直筋の短縮は非常に関連が深い
・ボールを蹴る動作が多いスポーツでは、下前腸骨棘の裂離骨折がしばしばみられる
・スプリンターに比較的多くみられる外傷に、大腿直筋の肉離れがある
・立位での腰椎前弯が強い例では、腸腰筋だけでなく大腿直筋の短縮にも気をつけなければならない
<関連する疾患>
大腿四頭筋拘縮症、Osgood-Schlatter病、jumper’s knee、下前腸骨棘裂離骨折、大腿直筋肉離れ、脊椎分離症、慢性腰痛症
筋の走行・機能
・股関節内転•外転軸のわずかに外側を通る⇨股関節の外転作用をわずかにもつ
・股関節屈曲•伸展軸の前方を通る⇨股関節の屈曲作用
・股関節内旋•外旋軸の前方を上外側に向かう⇨股関節のわずかな外旋作用をもつ
・膝関節の屈曲•伸展軸の前方を通る⇨膝関節の伸展作用をもつ
実際の触診法
【固定操作のポイント】
・股関節の伸展操作で骨盤が前傾する⇨反対側の股関節を屈曲位にして骨盤を後傾位に固定しておく
1.座位で行う方法
①座位にて下腿を下垂させ開始する。
②共同腱と内側広筋との筋腹上に指をおく。双方を同時に軽く圧迫し、組織硬度の違いを確認する。腱と筋との明らかな違いを感じ取る
③硬さを確認したら二等辺三角形状の共同腱を正確に触れる。左右の中指を腱の上に乗せる。
④重ねた指を内側へと移動させ、腱と内側広筋の違いを探る。正中側⇄内側にて境目を触診する。
⑤④の方法で正中側⇄外側にて外側広筋との境を触診する。
⑥近位へと移動させ、大腿直筋の筋腱移行部を確認する
⑦股関節の屈曲運動を行わせる(反復する)
⑧指は大腿直筋と共同腱の移行部にあて、股関節の屈曲運動に伴い大腿直筋が収縮する様子を触診する。
⑨屈曲運動を反復させ、大腿直筋の近位方向へと触れていく。大腿の中央部あたりでは幅約5cm前後の大腿直筋を内・外側から挟み込むように触れる。内側広筋と外側広筋との筋間も併せて確認するとよい。
2.背臥位で行う方法
①下前腸骨棘に指を置き、他動的に股関節を屈曲位とする。
②上記の状態で膝関節伸展または股関節屈曲を繰り返すことで大腿直筋の筋腹の緊張に触れることができる。
大腿直筋周辺の滑走性の獲得
大腿直筋の近位部は、下記により周囲を覆われている
表層:縫工筋
内側:腸腰筋
外側:大腿筋膜張筋と小殿筋
深層:大腿骨頭
股関節を屈曲する際に、腸腰筋による股関節外旋作用と小殿筋の股関節内旋作用による協調した働きが必要となる。そのため、両筋の間に位置する大腿直筋との滑走性を確認する必要がある。
[腸腰筋と大腿直筋間の滑走性の獲得]
a)表層にある縫工筋の内側から、腸腰筋と大腿直筋の筋間に指(縫工筋を外側にずらしてから)を入れる。大腿直筋の内側を触知し、対側の指で腸腰筋を固定する。
b)筋間に指を入れた状態で、膝関節の屈曲・伸展を繰り返すことで、腸腰筋と大腿直筋間の滑走性改善を図る
[小殿筋と大腿直筋間の滑走性の獲得]
a)縫工筋の外側から、大腿直筋と大腿筋膜張筋の筋間を分け、小殿筋と大腿直筋の筋間にゆびを入れる。
b)筋間に指を入れた状態で、膝関節の屈曲・伸展を繰り返すことで、小殿筋と大腿直筋間の滑走性改善を図る
ストレッチング
[全体像]
対象者を腹臥位とする。ベッドの左端に寄って左下肢をベッドから降ろし、左股関節を屈曲位に保持する。右股関節は軽度内転位とする。
セラピストは左手で対象者の右殿部を固定し、右手で右膝関節を屈曲し伸張する。
[固定操作]
セラピストの左手で対象者の右股関節を固定し、骨盤の直接的な固定とするが、その際は固定位置と骨盤後傾方向への固定が重要である。
[固定操作の詳細]
正しい位置の目安として、対象者の大転子を利用する。大転子部は大腿骨頭中心のやや下方。大腿骨頭中心が浮きあがりの頂点になるため、大転子のやや上方を抑える。